2025年11月24日更新
2026年1月からの新形式に対応して内容を更新しました。
TOEFL®の学習に役立つおすすめの参考書を紹介します。
本講座の授業では、主にここで紹介している参考書を使用します。
参考書タイトルのリンクから、Amazonの該当ページに移動することができます(リンクには細心の注意を払っていますが、万一誤りやリンク切れなどあれば、お問い合わせフォームからご連絡いただけると大変ありがたいです)。
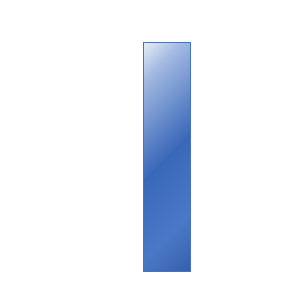 TOEFL問題集
TOEFL問題集
TOEFLの問題集は日本語でも出版されていますが、残念ながら日本語の問題集は収録されている問題数が少なく問題の質もあまり良くありません。
ここでは、定番の洋書の問題集を取り上げています。
2025年11月現在、新形式に対応した問題集はまだ出版されていません(本講座では、オリジナル教材なども交えて新形式の問題に対応した授業を提供しています)。
下で挙げている問題集もすべて旧形式のものです。
過去の傾向から推測すると、おそらく2027年頃から新形式対応の問題集が出てくるものと思われます。
新形式の問題に慣れる目的では他の教材を使うべきですが、旧形式の問題も多くは新形式受験のための実力養成に有効です。
したがって、次善の策ではあるものの、新形式対応の問題集が出てくるまでは引き続き旧形式の問題集を使用することをおすすめします。
ただし、新形式になったことで取り組む必要がほぼなくなったタスクもあります。
その辺りの取捨選択については本講座の授業で解説しています。
Official TOEFL iBT Tests, volume 1, ETS, 2024
TOEFLを運営するETSが発行している公式の問題集です。
収録されている問題は実際にTOEFLで出題されたことのある過去問であり、市販の問題集のなかでは当然ですがETS公式の問題集が最も問題の再現性が高いです。
五つのテストが収録されており、音声データなどは付録のアクセスコードを使ってウェブ上からダウンロードすることができます。
また、PC上で本番に近い形式での模試を受けることもできます。
TOEFL受験者にとっては、やはりETS公式の問題集は必携でしょう。
Official TOEFL iBT Tests, volume 2, ETS, 2024
上記と同じ問題集の第2巻です。
基本的な仕様はvol. 1と同じですが、vol. 2はスピーキングセクションの回答例を音声データで聴くことができます。
こちらも必携と言ってよいでしょう。
The Official Guide to the TOEFL iBT Test, seventh edition, ETS, 2024
こちらもETS公式の問題集で、基本的な仕様は上記の『Official Tests』と同様でスピーキングの回答例を聴くこともできます。
過去問が4題収録されているほか、本書はTOEFLの試験形式の解説や各セクションの練習問題を豊富に含んでおり、解答の解説も丁寧です。
タイトル通り、TOEFL初学者のためのガイドブックというところです。
TOEFLの問題集のなかでどれか一冊だけ選ぶとしたらこれでしょう。
ただし、当然英語で書かれているのでそもそも本書を丸ごと読み通すにはそれなりのリーディング力と時間が必要になります。
Practice Tests for the TOEFL iBT Test, third edition, Collins, 2024
非公式のTOEFL問題集としては定番の一冊です。
問題の音声データはダウンロードすることができますが、模試の形式でPC上で問題を解くことはできません。
収録されているテストは4回分です。
非公式の問題集としては問題のクオリティは高いのですが、それでもやはり本物のTOEFLと比べると細かな形式に違いも多く、違和感を覚えることもあります。
とはいえ、公式の問題集をやり尽くしてしまった、もしくは本番直前のために公式の問題集を温存しておきたいという場合には重宝するでしょう。
TOEFL iBT Premium, eighteenth edition, Barron's, 2024
Barron'sはアメリカ国内外向けに様々な分野の学習参考書を刊行している出版社で、TOEFL対策本も非公式のものとしては定番です。
Collins同様、問題の質は非公式のものとしては高いのですが、やはり細部で本物のTOEFLと異なるところも多く違和感はあります。
また、音声データやスクリプトはダウンロードできず、公式ウェブサイトに都度アクセスして利用する必要があるのですが、これが使いにくいです。
問題の質は高いのにこの点は残念です。
なお、模試形式でPC上で問題を解くことはできません。
もっとも、テスト収録数は8題と多いですし、各セクションの解説や練習問題も収録されていて、よい参考書であることには間違いありません。
こちらも、公式の問題集をやり尽くしてしまった、もしくは本番直前のために公式の問題集を温存しておきたいという場合に活用できるでしょう。
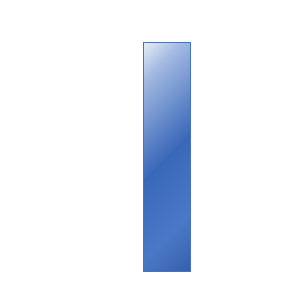 TOEIC問題集
TOEIC問題集
新形式になり、日常英語の重要度が飛躍的に上がりました。
この部分の対策としては、問題形式が非常に似ているTOEIC®(特にPart 2, 3, 7)の問題集に取り組むことが効果的です。
TOEICの場合は、国内にも優良な問題集が多くあります。
これは単なる次善策ではなく、今後もTOEFLの問題集はTOEICほど種類や量が豊富になるとは考えられないので、もしかすると新形式対応のTOEFL問題集が出てきても、特定のセクションに特化した問題としてはTOEIC教材を使い続けることが有効であり続けるかも知れません。
TOEIC L&R TEST パート1・2特急 難化対策ドリル、森田 鉄也、朝日新聞出版、2017年
TOEIC L&R TEST パート3・4特急 実力養成ドリル、神崎 正哉、朝日新聞出版、2017年
どちらも「特急シリーズ」の本で、特定のパートに特化した問題集です。
多くの問題が掲載されていて問題演習に役立ちます。
Part 2がTOEFLリスニングのListen and Choose a Responseタスク、Part 3がListen to a Conversationタスクと非常に類似しています。
価格が手頃で、コンパクトで使いやすいのもありがたいです。
TOEFLリスニングスコア3.5、TOEICスコア700点くらいのひとにおすすめです。
これよりも易しい問題集として同じシリーズの『初心者特急』シリーズもありますが、これはTOEIC 500点以下くらいの初級者向けで、このレベル帯であれば(TOEICよりもTOEFLの方に主眼があるという前提の場合)問題演習よりも単語学習と地力のリスニング力の強化にフォーカスする方が得策でしょう。
TOEIC L&R TEST パート1・2特急Ⅱ 出る問 難問240、森田 鉄也、朝日新聞出版、2018年
TOEIC L&R TEST パート3・4特急Ⅱ 実践トレーニング、神崎 正哉、朝日新聞出版、2017年
上掲本と同じシリーズですが、こちらの方がやや難しいです。
ただ、TOEFLを基準とした場合にはむしろちょうどよいくらいのレベル感です。
TOEFLリスニングスコア4以上、TOEICスコア800点以上くらいのひとにおすすめです。
TOEIC L&R テスト 究極のゼミ Part 7、ヒロ 前田、アルク、2017年
TOEIC Part 7に特化した問題集です。
このパートはTOEFLリーディングセクションのRead in Daily Lifeタスクと非常に類似しています。
解説が充実しているので、まだ試験慣れしていないひとが初めて取り組むのに適しています。
TOEFLリーディングスコア3.5以上、TOEICスコア600点以上くらいのひとにおすすめです。
解きまくれ! リーディングドリル TOEIC L&R TEST PART 7、大里 秀介、スリーエーネットワーク、2021年
こちらもTOEIC Part 7に特化した問題集です。
テスト8回分の問題が収録されていて、問題数が豊富ですが、その分解説は少ないです。
そのため、すでにある程度実力のあるひとが試験慣れしたいという場合に有効でしょう。
TOEFLリーディングスコア4以上、TOEICスコア700点以上くらいのひとにおすすめです。
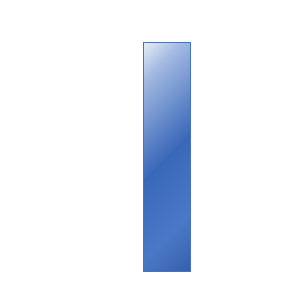 基礎レベル単語帳
基礎レベル単語帳
DUO 3.0、鈴木 陽一、アイシーピー、2000年
単語・熟語の基礎固めに最適です。
単語学習の王道は例文のなかで覚えること。
本書は良質な例文を通じて重要語句を効率よく覚えられるようにデザインされています。
TOEFLに限らず、英検®、TOEICなどどのような英語の試験を受けるにせよ本書の語彙は単語力の核になるでしょう。
TOEFLもバンドスコア4くらいまでならこれ一冊だけでも何とかなりますが、TOEFL特有の頻出語というものもあるので、本書に慣れてきたら早めに下記のTOEIC単語帳やTOEFL単語帳に移りましょう。
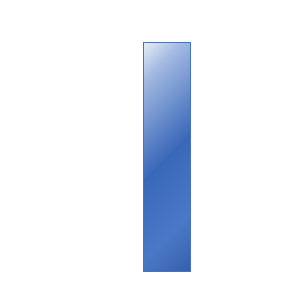 TOEIC単語帳
TOEIC単語帳
新形式ではアカデミックな内容の比重が大幅に減り、日常会話の比重が大きく増しました。
日常会話と言っても、何らかのかたちで特にビジネスに関わる問題が多いです。
ただし、その対策のためにビジネス英語の参考書を使うと、専門的になり過ぎて無駄が多くなってしまいます。
新形式の問題傾向からすると、(意図的にそうしているのかも知れませんが)TOEICの対策本がこの点では最適です。
単語帳もこの例に漏れません。
ただし、TOEFL対策を第一目的とする場合には、普通にTOEIC対策を目的とする場合とは単語帳の選び方が違ってくるので注意が必要です。
TOEIC®L&R TEST英単語スピードマスター mini☆van 3000、成重 寿、Jリサーチ出版、2021年
TOEFL対策を目的としてTOEIC単語帳を使うなら本書が最もおすすめです。
オールインワンレベルで幅広い単語とイディオムが掲載されているほか、「ビジネス語」と「生活語」がまとまっていることが最大の利点です。
TOEFL単語学習の準備になるだけでなく、TOEFL単語帳の弱いところを補完することができます。
TOEICでは出題されない意味が載っていることもありますが、TOEICに寄せ過ぎない姿勢はTOEFL対策としてはむしろメリットです。
多くの語に例文と解説がありますが、これらが無い語もあるのが玉に瑕でしょうか。
なお、『mini van』表記が無いものもありますが、これは本書の旧版です。
mini vanの方がカラフルな印刷で見やすく、コンパクトで使いやすいので、mini vanを選んでおけば問題ありません。
ただ、mini vanの音声はダウンロードのみとなっているのに対して旧版にはCDが付属するので、CDが欲しい場合は旧版を選ぶのもよいでしょう。
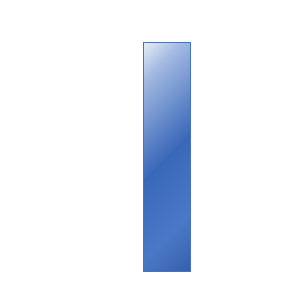 TOEFL単語帳
TOEFL単語帳
問題集とは事情が異なり、TOEFL対策に特化した単語帳は国内のものも大変充実しています。
良書もたくさんありますが、ここではそのなかでも代表的なものを紹介しましょう。
ただし2025年11月現在、(たとえ「新形式対応」と銘打っていても)いずれも旧形式を想定したもので、新形式の単語の出題傾向には即していません。
そのため、単独で使うのではなく、まずは上で紹介したような基礎レベル単語帳やTOEIC単語帳に習熟することを優先し、TOEFL単語帳はそのうえでアカデミックな単語を上積みする目的で使いましょう。
完全攻略! TOEFLテスト英単語4000、河野 太一、アルク、2014年
最もおすすめです。
単語の記憶を定着させるコツは、とにかくその語に様々な観点からアクセスできる取っかかりを増やすことです。
その点、本書はレベル別、分野別に単語をグルーピングしており、ひとつひとつの語に語呂合わせや語源、類義語などの豆知識を記載していて、覚えやすい工夫をこらしています。
収録語彙数も多いので、ハイスコアまで狙えます。
TOEFLテスト英単語3800、4訂版、神部 孝、旺文社、2014年
旺文社といえば学習参考書で有名な出版社であり、日本語のTOEFL対策本として言わずと知れた「TOEFLテスト大戦略シリーズ」もここです。
本書もこのシリーズの一冊で、TOEFL単語帳としては定番です。
例文が多いのは助かりますが、本編の単語の掲載順にあまり規則性がないのが気になります。
別冊付録の小冊子は、アカデミックな内容の日本語のパッセージのなかで分野別に単語を覚えられるようになっており、こちらは使いやすいです。
TOEFL必須英単語5600、林 功、ベレ出版、2011年
旧形式では、一定以上のスコアを狙う受験者に最もおすすめしていたのが本書でした。
ですが、アカデミックな単語に関しては新形式では重要度が大幅に減り、求められるレベルも易化したため、アカデミックな語を中心に掲載語数がとても多い本書にあえて手を出す意味はあまりなくなってしまいました。
個人的にも最も愛用していた単語帳が本書なので、寂しいものですね。
新形式でも、リーディングセクションで本気で満点を取りに行く場合や、単語力を武器にしたい場合には、本書に取り組んでみてもよいかも知れません。
本書は何といっても語彙数が多く、やり通せば自信が付くでしょう。
キャンパスライフ関係の語も充実しています。
PART 1とPART 2に分かれていて、PART 1はアカデミックな内容のパッセージが収録されており、そのパッセージのなかで単語を覚えるという構成になっています。
アカデミックな英語に慣れることができ、CDを使えばリスニング練習にもなって一石三鳥です。
本書の欠点を挙げるなら、誤植が多いことと、TOEFLにもまず出題されないであろうマニアック過ぎる語彙が含まれていることでしょう。
とはいえ、誤植はすぐに気づけます。
語彙の問題に関しても、PART 2の主に建築と医学の語彙のうち、日本語でも意味が分からない語は飛ばせばいいのです。
また、sodium, tinなどの物質名や生物名、病名などは日本語と一対一対応させて覚えるのではなく、その語が出てきたときに「これは物質の名前だな」、「これは病気の名前だな」ということが分かれば十分でしょう。
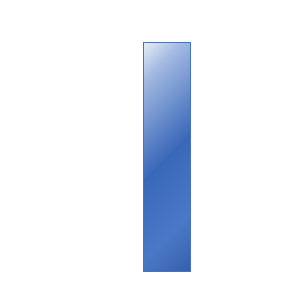 熟語帳
熟語帳
熟語(イディオム)は単語と比べるとどうしても地味で後回しにされがちですが、TOEFLを攻略するためにはそれなりの熟語の知識も不可欠です。
おろそかにしないようにしましょう。
システム英熟語、5訂版、霜 康司・刀祢 雅彦、駿台文庫、2019年
熟語を覚える秘訣は、単なる語の羅列ではなく、中心となる語や前置詞、類似表現などの関連を意識して、グルーピングでまとめて覚えることです。
本書はこのようなグルーピングを意識した構成となっていておすすめです。
受験参考書としても有名な一冊です。
英熟語ターゲット1000、5訂版、花本 金吾、旺文社、2021年
こちらも、大学受験参考書として定番の熟語帳です。
重要なイディオムが網羅的にカバーされています。
ただこれは個人的な感覚かも知れませんが、昔の3訂版の頃のレイアウトの方が、熟語のグループ分けが明瞭で分かりやすかったような……?
コレ以上やる必要はない英熟語1000、長野 順一・阪元 利和、KADOKAWA、1999年
本書はTOEFL中~上級に最適なレベル感で、構成は語形や意味のグルーピングを強く意識して体系的にまとまっており、細かいところに手が届く注釈にも好感が持てます。
非常に使いやすい良書です。
残念ながら現在絶版なので、見つけたら手に入れておくことをおすすめします。
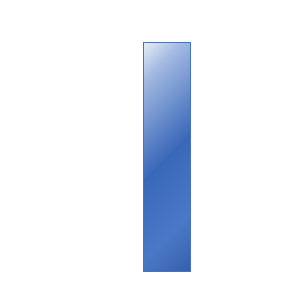 文法書
文法書
総合英語Evergreen、川崎 芳人・久保田 廣美・高田 有現・高橋 克美・土屋 満明・Guy Fisher・山田 光、いいずな書店、2017年
大学受験英語の文法書と言えばおそらく一番有名な参考書でしょう。
評判通りの優れた著作です。
TOEFL対策としても基本の一冊としておすすめです。
色々な文法書をハシゴするよりも、本書を繰り返し読み込む方が有益。
内容はスタンダードな構成になっています。
「そもそも~とは?」というところから丁寧に分かりやすく説き起こし、初級~中級レベルの文法知識が過不足なく身につきます。
中・上級者にとっても応用編の記述はなかなか侮りがたいものがあるので、その辺りを中心に読み返すと色々発見があるはずです。
一億人の英文法、大西泰斗・ポール マクベイ、東進ブックス、2011年
こちらも説明不要の名著です。
読者の素朴な疑問に答え、英語の根源的な構造を感覚的に分かるように説明する、かゆいところに手が届く一冊。
基本的には初級者向けに書かれていますが、中・上級者にとっても目から鱗が落ちる記述が多くあるはずなので、なるべく早い段階で一度は目を通しておくとよいです。
ネイティブライクな例文も、中・上級者にとってはむしろ好都合でしょう。
また、文章、レイアウト、イラストなどすみずみにまで読みやすさのための配慮がなされていて、内容が自然に頭に入ってきます。
ただ、内容の構成や用語が独特なので、他の文法書との互換性や深い文法的な理解には問題もあります。
そのため、他の文法書と組み合わせて読むことで真価を発揮するでしょう。
徹底例解ロイヤル英文法、改訂新版、綿貫 陽・宮川 幸久・須貝 猛敏・高松 尚弘、旺文社、2000年
Evergreenなどの大学受験用文法書で物足りなくなってきたらこちら。
英語のプロもしばしば参照する網羅的な文法書です。
文法学者になるのでもなければ、英文法に関してはこれ一冊で一生困らないでしょう。
文法で分からないことがあったときに確認するという仕方で、辞書的に使うのが基本です。
ですがTOEFLリーディングセクションで5.5以上を目指す上級者は、もし時間が許すなら、本書を一度は通読してみることをおすすめします。
時間はかかりますが、それに見合う価値はあります。
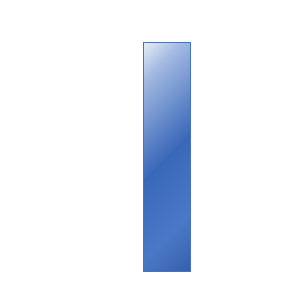 ライティング
ライティング
英語ライティングルールブック 改定新版、デイビッド・セイン、Gakken、2024年
ライティングでバンドスコア5以上のハイスコアを狙うなら一度は目を通しておくことをおすすめします。
第一章の文法事項は上記の『Evergreen』や『ロイヤル英文法』を読んでいれば真新しい内容はありませんが、特に第二章の語法と第三章の句読法はライティング対策に有用です。
ライティングの主な評価基準は全体の論理構成や文章の意味が通るかどうかなので、細かな句読法については、対策における優先度は高くありません。
ただ、新形式ではこうした細かな正確性のウェイトがやや増したようにも感じます。
いずれにせよ、正確で自然な表現を身に付けておくことはもちろんスコアアップに繋がります。